慶應義塾大学 医学部の化学対策
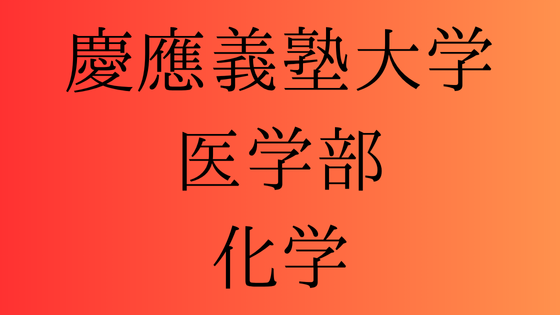
本記事では慶應義塾大学の医学部の化学対策について記載しています。
慶應義塾大学の医学部は一次試験と二次試験にわかれており、一次試験は英語・数学・理科(物理、化学、生物から2科目選択)の試験で、二次試験は小論文と面接です。
私立大学の医学部の中でもトップレベルであり、6年間の費用も私立大学の中では比較的少ないということもあり、非常に人気です。
東京大学をはじめとした難関国立大受験生も受けるので、倍率と受験者層を考えると熾烈な戦いになります。
医学部の化学は理科2科目で試験時間は120分で、配点は200点です。
合格最低点は60%弱ですので、化学が得意な受験生は70%以上、苦手な受験生でも50%以上得点したいところです。
医学部の入試情報
| 年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 |
| 2025 | 66 | 1,410 | 1,284 | 177 | 7.3 | 280/500(56.0%) |
| 2024 | 66 | 1,483 | 1,270 | 169 | 7.5 | 319/500(63.8%) |
| 2023 | 66 | 1,412 | 1,219 | 168 | 7.3 | 315/500(63.0%) |
| 2022 | 66 | 1,388 | 1,179 | 178 | 6.6 | 308/500(61.6%) |
| 2021 | 66 | 1,248 | 1,045 | 242 | 6.1 | 251/500(50.2%) |
各項目の傾向と対策
大問は全部で3つです。
大問ごとの問題と構成は下の表を参照してください。
| 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | |
| Ⅰ | ・有機化合物の構造式 設問×5 | ・DNA、窒素化合物、アンミン錯イオン、COD 設問×3 | ・小問集合 設問×6 |
| Ⅱ | ・塩化ナトリウムの電気分解、水素の体積、アンモニアの沸点、アンモニアから水素を取り出す研究 設問×4 | ・有機化合物の構造式決定、ナイロン66、異性体 設問×4 | ・KFe[Fe(CN)6]、フェロシアン化銅(Ⅱ)の製造、浸透圧の測定 設問×7 |
| Ⅲ | ・メーオーの実験装置 設問×5 | ・気体の熱膨張、分圧、気体の発生、硫酸製造 設問×4 | ・アミノ酸の性質、ペプチドのアミノ酸配列 設問×8 |
理論化学、有機化学は確実に出題されていますが、年度によって難易度が大きく変わります。
難易度自体も難しい知識が出題される年度や計算の難易度が高い年度があり、どのような難易度なのかやどんな種類の難しさなのかを予測することが難しい学部です。
問題が開始された後に確認して難易度が標準的であれば高得点勝負、明らかに難しい場合は確実に取れる問題をとっていく戦略になります。
●対策
理論化学は幅広い分野から出題されています。
計算の難易度が高い年度もあり、事前に難易度の高い問題にも触れておかないと、対応できずそのまま他の受験生との差になる可能性が高いです。
無機化学は上位の大学では定番となっていますが、理論化学との融合問題が出題される傾向にあります。
有機化学は非常に難易度の高い問題が出題されることもあるので、慶應大学を専願で受験する人は東京大学や京都大学で出題される難易度の高い問題も事前に解いておく必要があります。
まず教科書や基本的な参考書を軽く1周して概要を掴んでから、2周目以降で内容を頭に入れていきましょう。
必ずしも全部頭に入れてから問題を解く必要はなく、単元ごとに問題集で演習を積んでいってもいいでしょう。
資料集も活用し、ビジュアルで理解するように心がけてください。
問題は『化学重要問題集』、『化学の新演習』、『化学標準問題精講』などの難易度の高い問題集を使って演習を積んでいきます。
『化学の新研究』などで詳細に調べていくと発展的な力を身につけることができます。
最後は過去問を使って制限時間内に解き切れるかを確認していきます。
最低5年分は取り組み、終わったら年度を遡ってもいいですし、東京大学や京都大学、他の私立医学部の問題を解いていっても効果的です。
早慶上理対策のまとめはこちら!↓

