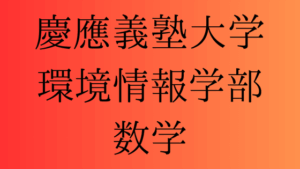慶應義塾大学 医学部の数学対策
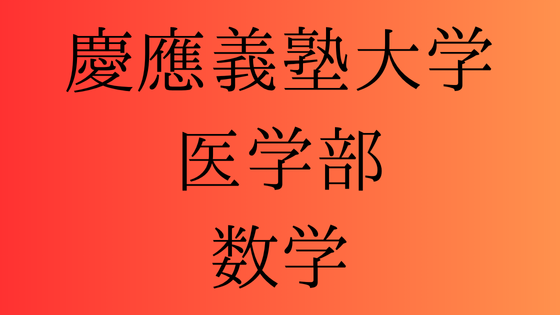
本記事では慶應義塾大学の医学部の数学対策について記載しています。
慶應義塾大学の医学部は一次試験と二次試験にわかれており、一次試験は英語・数学・理科(物理、化学、生物から2科目選択)の試験で、二次試験は小論文と面接です。
私立大学の医学部の中でもトップレベルであり、6年間の費用も私立大学の中では比較的少ないということもあり、非常に人気です。
東京大学をはじめとした難関国立大受験生も受けるので、倍率と受験者層を考えると熾烈な戦いになります。
医学部の数学の試験時間は100分で、配点は150点です。
合格最低点は60%弱ですので、数学が得意な受験生は70%以上、苦手な受験生でも50%以上得点したいところです。
医学部の入試情報
| 年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 |
| 2025 | 66 | 1,410 | 1,284 | 177 | 7.3 | 280/500(56.0%) |
| 2024 | 66 | 1,483 | 1,270 | 169 | 7.5 | 319/500(63.8%) |
| 2023 | 66 | 1,412 | 1,219 | 168 | 7.3 | 315/500(63.0%) |
| 2022 | 66 | 1,388 | 1,179 | 178 | 6.6 | 308/500(61.6%) |
| 2021 | 66 | 1,248 | 1,045 | 242 | 6.1 | 251/500(50.2%) |
各項目の傾向と対策
大問は全部で4つです。
大問ごとの問題と構成は下の表を参照してください。
| 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | |
| Ⅰ | ・小問集合 1. 確率分布 2. 確率密度関数 3. 極限計算 4. 複素数平面 5. 整数問題 | ・小問集合 1. 三角形の五心、点の座標 2. 楕円、不等式の証明 3. 最大値・最小値、面積 | ・小問集合 1. 平面ベクトルの内積 2. 複素数平面、ド・モアブルの定理 3. 接線と法線、面積 |
| Ⅱ | ・確率漸化式、確率分布 設問×2 | ・確率と漸化式 設問×2 | ・独立・反復試行の確率 設問×4 |
| Ⅲ | ・恒等式、関数の増減 設問×2 | ・関数の増減と極値、関数の極限 設問×5 | ・接線と法線、漸化式、無限等比級数 設問×5 |
| Ⅳ | ・平面図形、空間図形 設問×2 | ・点の座標(空間)、体積 設問×4 | ・最大値・最小値、加法定理とその応用 設問×4 |
大問1は小問集合で大問2~4は応用的な内容もしくは融合問題です。
解答形式は穴埋めであることが多く、記述や論証の問題は少ないです。
大問1と2は標準的な問題ですが、大問3と4の難易度が非常に高いです。
全体的に計算量と処理量が多いため、難易度の判断と時間配分が合否の分かれ目になります。
2025年度では確率統計から出題されているので、今後も幅広い範囲の応用的な学習が必要です。
●対策
まずは『青チャート』などの網羅的な問題集を使って典型的な問題なら瞬時で解けるという状態にします。
公式の導出方法や明確な定義の確認を飛ばさずに一つ一つ丁寧に理解していきましょう。
本学部の数学は素早く計算を行っていくことが重要なので、素早い計算の練習や省ける計算を判断する力を『合格る計算』シリーズなどを使って身につけていきます。
『青チャート』よりレベルが高い典型問題を学習したい場合は『一対一対応』シリーズを使いましょう。
この段階では熟考するよりも、手際よく解法を身につけていくことに集中してください。
数学が好きな受験生はここでいろいろな解法や自力で解くことにこだわる傾向にありますが、あくまで期日までに合格する力を身につけることが受験では重要なので割り切って学習していきましょう。
上記の学習を終えたら、『上級問題精講』や『やさしい数学』などの応用的な理系数学が解ける問題集をやっていきましょう。
この段階では時間無制限で熟考する練習を積んでいきましょう。
受験が迫っているときは中々熟考の時間が取れませんが、9~11月時点であれば、熟考に時間を割いてもいいでしょう。
最後に過去問を使って仕上げていきます。
実際に時間を計って、典型問題と難易度の高い問題の区別と手際よく解答までたどり着く練習をしていきます。
最低でも5年分はやり、余力があれば東京大学や東京慈恵会医科大学、日本医科大学などの医学部の問題を解いていきましょう。
早慶上理対策のまとめはこちら!↓