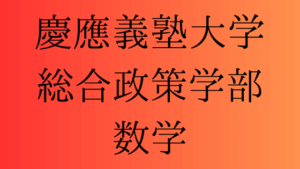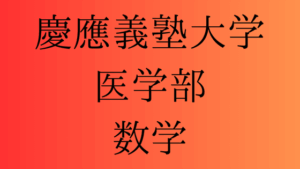慶應義塾大学 環境情報学部の数学対策
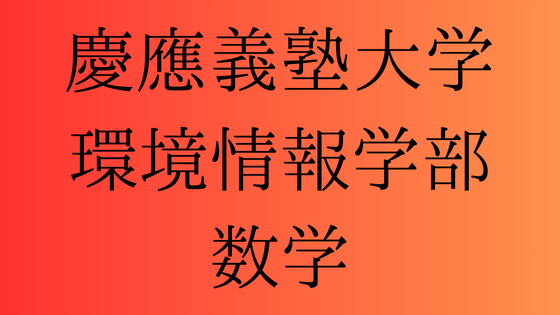
本記事では慶應義塾大学 環境情報学部の数学対策について記載しています。
環境情報学部の数学の試験時間は120分で、配点は200点です。
数学の出題範囲は数学Ⅰ、数学A(図形の性質・場合の数と確率・数学と人間の活動)、数学Ⅱ、数学B(数列・統計的な推測)、数学Ⅲ、数学C(ベクトル、平面上の曲線と複素数平面)です。
目標得点率は70%以上に設定して勉強していきましょう。
環境情報学部の入試情報
| 年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 |
| 2025 | 225 | 2,446 | 2,169 | 376 | 5.8 | 250/400(62.5%) |
| 2024 | 225 | 2,287 | 2,048 | 380 | 5.4 | 259/400(64.7%) |
| 2023 | 225 | 2,586 | 2,319 | 362 | 6.4 | 246/400(61.5%) |
| 2022 | 225 | 2,742 | 2,450 | 446 | 5.5 | 238/400(59.5%) |
| 2021 | 225 | 2,864 | 2,586 | 336 | 7.7 | 238/400(59.5%) |
各項目の傾向と対策
大問は全部で5つです。(2023年度は大問が6つです)
大問ごとの問題と構成は下の表を参照してください。
| 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | |
| 数学Ⅰ | ・小問集合 1. 数列 2. 放物線と円 | ・小問集合 1. 不等式の証明 2. 指数・対数不等式、不等式の証明 | ・小問集合 1. ユークリッド互除法 2.不定方程式 |
| 数学Ⅱ | ・四角柱 設問×4 | ・場合の数、いろいろな数列 設問×4 | ・定積分、接線・法線 設問×1 |
| 数学Ⅲ | ・複素数平面 設問×4 | ・空間ベクトルと図形、空間ベクトルの内積 設問×1 | ・不定方程式、確率の基本性質 設問×2 |
| 数学Ⅳ | ・積分、体積 設問×2 | ・球面の方程式、体積 設問×3 | ・場合の数、確率の基本性質 設問×2 |
| 数学Ⅴ | ・確率の基本性質 設問×1 | ・確率の基本性質 設問×2 | ・点の座標(空間) 設問×4 |
| 数学Ⅵ | ・2次関数の最大・最小 設問×2 |
全問マーク式です。
微積分、図形・図形と式、確率・場合の数、整数の性質が頻出分野です。
120分ですが、大問の数を考えると1題あたり24分弱しかかけることができません。
●対策
『青チャート』などの網羅的な問題集で典型的な問題を瞬時に解けるようにしていきましょう。
本学部の数学は一般的な状況を数学的に考える問題も出題されますが、ほとんどが一般的な数学の勉強で対処できます。
難しい問題を解けるようにするよりも、基本~標準レベルの問題を素早く正確に解けるようにすることの方が重要です。
確率に関する問題は毎年必ず出題されるので、解けるように練習を重ねるべきですが、どうしても特定の解法があてはまるとは限らず、一から自分の力で考えなければならない要素もあるので、最後まで克服できない場合は他の問題で点を取るようにしましょう。
典型的な問題を解けるようになったら、『文系数学の良問プラチカ』などの応用問題集をやり、最後に過去問演習をしていきましょう。少なくとも5~10年分は解きますが、前提として所有している過去問には全て触れるようにしましょう。
環境情報学部の問題を解き終えたら、総合政策学部の問題にチャレンジみるとさらに力がつくでしょう。
早慶上理対策のまとめはこちら!↓