慶應義塾大学 法学部の小論文対策
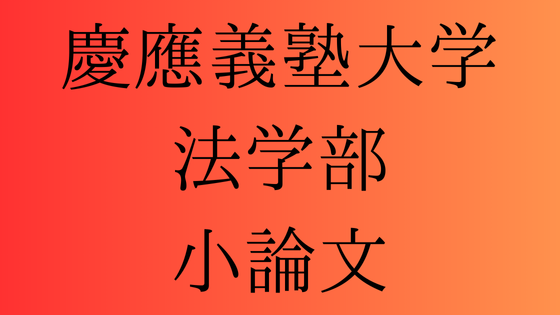
本記事では慶應義塾大学 法学部の小論文(論述力)対策について記載しています。
2024年度までの小論文の試験時間は90分で、配点は100点です。
2025年度入試から試験時間は90分から60分になり、名称も「論述力」から「小論文」に変更になります。
英語、社会の点数が基準点に満たない場合、小論文は採点されませんのでご注意ください。
法学部の入試情報
| 年度 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点 |
| 2024 | 法律 | 230 | 1,657 | 1,466 | 380 | 3.9 | 243/400(60.7%) |
| 政治 | 230 | 1,363 | 1,212 | 324 | 3.7 | 247/400(61.7%) | |
| 2023 | 法律 | 230 | 1,730 | 1,569 | 352 | 4.5 | 247/400(61.7%) |
| 政治 | 230 | 1,407 | 1,246 | 329 | 3.8 | 252/400(63.0%) | |
| 2022 | 法律 | 230 | 1,853 | 1,633 | 378 | 4.3 | 239/400(59.7%) |
| 政治 | 230 | 1,323 | 1,190 | 301 | 4.0 | 236/400(59.0%) | |
| 2021 | 法律 | 230 | 1,359 | 1,243 | 336 | 3.7 | 234/400(58.5%) |
| 政治 | 230 | 1,603 | 1,441 | 344 | 4.2 | 235/400(58.7%) |
傾向と対策
2023年度まで社会科学・人文科学の領域から読会資料が与えられ、それに対して論述形式で解答する問題でした。
2024年度では2人の対話に参加する形で自分がどんな発言をするのかを500字以内で2箇所答える問題に変わっています。
2025年度の試験形式の変更のヒントになると思いますので、過去問の中でも2024年度の問題を注視しておきましょう。
法学部は冒頭で下記のとおり評価の対象が書いてあります。
「読解資料をどの程度理解しているか(理解力)、理解に基づく自己の所見をどのように論理的に構成するか(構成力)、論述の中にどのように個性的・独創的発想が盛り込まれているか(発想力)、表現がどの程度正確かつ豊かであるか(表現力)が評価の対象となる」
この4つの基準を丁寧に満たしていけば、合格点を取ることができます。
子どもっぽい文章だったり、感情論だけで論理が破綻していたり、文章の内容をそのまま書いたような形になっていたりすると大きく減点されます。
●過去4年分の出典
| 年度 | 問題の出典 |
| 2025 | ローマ法大全に関する学説 |
| 2024 | 『政治的対話篇』モーリス・クランストン |
| 2023 | 『なめらかな社会とその敵』鈴木健 |
| 2022 | 『直言、そして考察ー今日の政治的関心』田中美知太郎 |
| 2021 | 「一匹と九十九匹とーひとつの反時代的考察」『福田恒存全集』福田恒存 |
●評価基準ごとの対策
・2025年度「小論文」の出題
法と正義に関して、ローマ法大全に収録されている学説をもとに「法律の適用は正義の尊重と両立可能であるか」について800字以内で客観的に論じるという問題でした。
普遍的な例を論拠とする必要があるので、その場で考えた自分の経験などを元に論述することができないため、非常に難易度が高い問題です。
とはいえ、2024年度までの論述力試験も難易度の高いもので、法学や政治学に関する文章から出題されているため、過去問演習は無駄になりません。相変わらず、基本的な戦略は英語と社会で高得点をとることが最適となりそうです。
・理解力
文章の内容がかなり難しいので、まずは読解力を身につける必要があります。
小論文の勉強を始める前に現代文の勉強をしましょう。
はじめは選択式の問題集でもいいのですが、国公立向けの記述式の問題集にシフトしていくと力がついていきます。
文章を読み終わったら、毎回要約するようにしましょう。
要約は文章の言葉をそのまま使って短くすることではなく、「要するに何を伝えたいのか」を抽象化してまとめ上げる作業です。
要約内容に不安があるときは先生や講師などに添削してもらうようにしてください。
・構成力
文章を書き出す前に構成を書くようにしましょう。
どういう構成にするかを決めずに書き出すと内容が散逸的になって、何を言いたいのかわからない文章になってしまいます。
要約+自分の考えという二部構成をスムーズに描けるように最低10年分以上は過去問で演習を積んでおきましょう。
・発想力
個性的・独創的発想というのは論理破綻した突拍子もないことを指していません。
視点が個性的・独創的ということです。
この視点を表現するには、まず内容を抽象化して要約する必要があります。
やはり「つまり何が言いたいのか」に対する理解力の有無が影響します。
・表現力
文章の表現をそのまま使ったり、小中学生みたいな語彙しか使えなかったりすると減点されます。
むやみに難しい言葉を使う必要はありませんが、そもそも文章の内容が難しいので、それを踏まえて要約したり自分の意見を述べるとなると、表現が高度になります。
『日本語チェック2000』などの日本語の語彙を強化できるようなものを使って対応しましょう。
社会科学や人文科学に対する知識も重要ですが、何にせよ小論文の基本をおさえて、どれだけ問題演習+添削をやってきたかが問われる試験です。
最低10年分以上の過去問を通じて、法学部の小論文で求められる解答にできるだけ近づけるようにしていきましょう。
早慶上理対策のまとめはこちら!↓
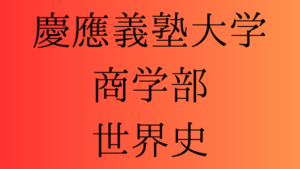
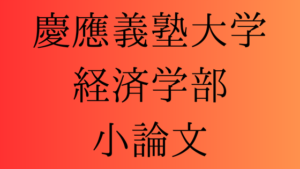
“慶應義塾大学 法学部の小論文対策” に対して1件のコメントがあります。
コメントは受け付けていません。