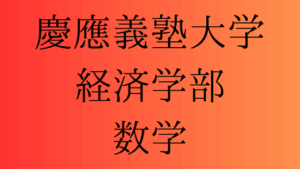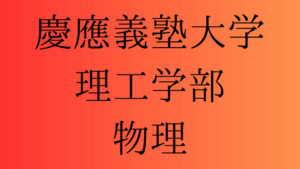慶應義塾大学 理工学部の数学対策
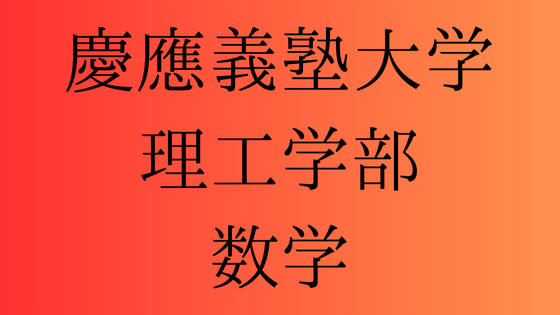
本記事は慶應義塾大学の理工学部の数学対策について記載しています。
理工学部の数学の試験時間は120分で、配点は150点です。
合格最低点は60%程度で推移していますので、目標得点率は70%以上に設定して勉強していきましょう。
数学が得意な人は80%以上の得点率を目標に勉強していきましょう。
理工学部の入試情報
| 年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 | 合格最低点 |
| 2026 | 650 | 8,461 | ||||
| 2025 | 650 | 8,637 | 8,139 | 2,728 | 3.0 | 297/500(59.4%) |
| 2024 | 650 | 8,248 | 7,747 | 2,495 | 3.1 | 321/500(64.2%) |
| 2023 | 650 | 8,107 | 7,627 | 2,452 | 3.1 | 290/500(58.0%) |
| 2022 | 650 | 7,847 | 7,324 | 2,641 | 2.8 | 340/500(68.0%) |
| 2021 | 650 | 7,449 | 7,016 | 2,309 | 3.0 | 266/500(53.2%) |
各項目の傾向と対策
大問は全部で5つです。
大問ごとの問題と構成は下の表を参照してください。
| 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | |
| ・小問集合 設問×3 | ・小問集合 設問×2 | ・微分係数、平均値の定理 設問×3 | |
| ・座標平面の図形、接線、ベクトル 設問×3 | ・確率の基本性質、条件付き確率 設問×5 | ・点の座標(空間)、空間ベクトルの内積 設問×3 | |
| ・確率の基本性質、漸化式、数学的帰納法 設問×4 | ・定積分と不等式、微分法の不等式への応用 設問×5 | ・確率の基本性質、確率と漸化式 設問×3 | |
| ・定積分、不等式 設問×5 | ・空間ベクトルと図形、空間ベクトルの内積 設問×3 | ・数列との融合、定積分 設問×5 | |
| ・図形と数、整数の最大値・最小値 設問×1 | ・複素数の極形式、曲線の長さ 設問×4 | ・小問集合 設問×2 |
マーク式と記述問題が大問内で混合して出されます。
記述問題は証明、論述問題であることが多いので過去問で演習を積んでおきましょう。
問題文、計算量、設問量が多いので、120分という時間内で手際よく難易度の判断と典型問題の処理をしていく必要があります。
●対策
『青チャート』などの網羅的な問題集を使って典型問題を素早く処理できるようにしていきましょう。
数学が得意な人は初見で解けそうな問題は飛ばして、効率よく前に進めていきましょう。
計算に不安がある人は時間がかかりますが、1問ずつ最後まで解ききってください。
数学ⅢCからの出題が目立つのでⅠAⅡBの基本には早めに取りかかって、ⅢCが中途半端なまま入試に臨まないようにする必要があります。
ⅢCはⅠAⅡBを基礎としているので、基礎をおろそかにしたままⅢCの学習を始めてもあまり意味がありません。
理工学部は英語の難易度が高い分、基本~標準レベルの問題が多い数学では、ある程度、高得点を取る必要があります。
典型問題の処理スピードをあげる、計算力をあげる、記述力をあげるということを念頭に置きながら勉強していきましょう。
難易度の高い問題に挑戦するのはこれらができてからです。
最後は過去問を使用して理工学部の形式に慣れていきましょう。
早慶上理対策のまとめはこちら!↓