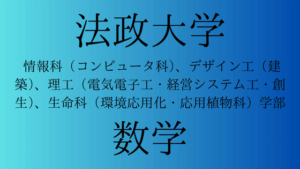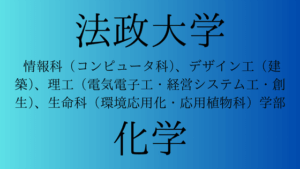法政大学 情報科(コンピュータ)、デザイン工(建築)、理工(電気電子工・経営システム工・創生)、生命科(環境応用化・応用植物)学部の物理対策
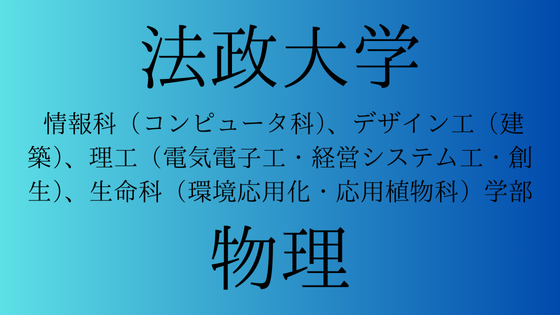
本記事では法政大学 情報工・デザイン工・理工・生命科学部(Ⅱ日程)の物理対策について記載しています。
2月14日に実施される情報工学部A方式Ⅱ日程(コンピュータ科学科)、デザイン工学部A方式Ⅱ日程(建築学科)、理工学部A方式Ⅱ日程(電気電子工・経営システム工・創生科学科)、生命科学部A方式Ⅱ日程(環境応用科・応用植物科学科)の英語です。
物理の試験時間は75分で、配点は150点です。
目標得点率は70%以上に設定して勉強しましょう。
情報工・デザイン工・理工・生命科学部の情報(Ⅱ日程)
法政大学の公式サイトを参照してください。
各項目の傾向と対策
大問は全部で4つです。
大問ごとの問題と構成は下の表を参照してください。
| 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | |
| Ⅰ | ・斜面への衝突、慣性力 設問×9 | ・ばねと衝突 設問×9 | ・斜面上の小物体の放物運動、円運動 設問×9 |
| Ⅱ | ・相互誘導、自己誘導 設問×7 | ・電界と電位、ガウスの法則 設問×7 | ・自己誘導と相互誘導、交流と変圧器 設問×7 |
| Ⅲ | ・等温変化、断熱変化 設問×7 | ・熱気球 設問×7 | ・内部エネルギーの保存 設問×7 |
| Ⅳ | ・音の3要素 設問×7 | ・波の式とグラフ 設問×7 | ・回折格子、光のドップラー効果、恒星の運動 設問×7 |
力学、電磁気学、熱力学、波動から出題されています。
ほとんどの問題が記述式で、空所を埋める誘導形式と小問の解答を記述する設問形式があります。
ほとんどが標準的なレベルですが、中にはやや難しい問題や計算量の多い問題が含まれます。
75分という時間を考えると素早く解いていく必要があります。
●対策
まずは教科書レベルの内容を理解していきましょう。
公式を丸暗記せずに図などを使って人になぜそうなるのかを説明できるようになるまでにしておいてください。
次に『基礎問題精講』などを使って基本的な典型問題を身につけていきます。
上記の問題集が終わったら『良問の風』や『重要問題集』などの応用問題を解いていきます。
間違えた問題はミスをした部分を分析して徹底的に理解していきましょう。
公式などの使いどころをマスターしたあと、物理で高得点を狙っている場合は『名問の森』などの発展的な問題を自力で解ききれるか確認してください。
ここで解答をみてわかった、理解した=解けると判断する人がいるので、ご注意ください。
最後に過去問を使って仕上げていきます。
過去問演習をするときは問題集を解くときと同じく、失点分析を欠かさないようにしてください。
その問題を理解するだけでなく、次回につなげる形で理解できるかがポイントです。
GMARCH対策のまとめはこちら!↓