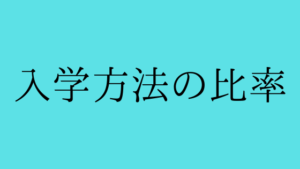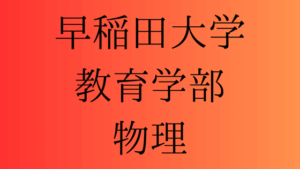早稲田大学 教育学部の化学対策
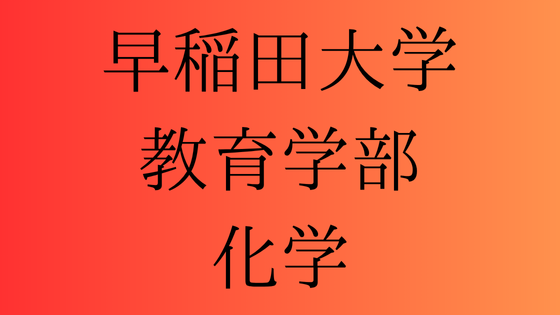
本記事は早稲田大学教育学部の化学対策について記載しています。
早稲田大学教育学部は教育学科、国語国文学科、英語英文学科、社会科、理学科、数学科、複合文化学科にわかれています。
英語英文学科、複合文化学科は英語の得点調整後の点数を1.5倍にして合否判定をします。
国語国文学科は国語の得点調整後の点数を1.5倍にして合否判定をします。
数学科は数学の得点調整後の点数を2倍にして合否判定をします。
早稲田大学教育学部の化学の試験時間は60分、配点は50点です。
合格最低点は60%前後で推移しているので、目標得点率は70%以上(35/50点以上)に設定して勉強をしましょう。
教育学部の入試情報(一般選抜 A・B方式)
| 年度 | 学部 | 学科 | 専攻など | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 | 合格最低点 |
| 2025 | 教育 | 教育学 | 教育学 生涯教育学 教育心理学 | 95 | 981 | 909 | 120 | 7.6 | 95.095/150(63.4%) |
| 1,006 | 943 | 65 | 14.5 | 97.558/150(65.0%) | |||||
| 623 | 568 | 64 | 8.9 | 97.884/150(65.3%) | |||||
| 初等教育学 | 20 | 427 | 388 | 41 | 9.5 | 92.677/150(61.8%) | |||
| 国語国文 | 80 | 1,405 | 1,341 | 200 | 6.7 | 108.385/175(61.9%) | |||
| 英語英文 | 80 | 1,451 | 1,369 | 313 | 4.4 | 109.126/175(62.4%) | |||
| 社会 | 地理歴史 公共市民学 | 140 | 1,802 | 1,683 | 206 | 8.2 | 100.365/150(66.9%) | ||
| 1,738 | 1,653 | 299 | 5.5 | 94.030/150(62.7%) | |||||
| 理 | 地球科学 | 20 | 821 | 711 | 100 | 7.1 | 92.250/150(61.5%) | ||
| 数 | 45 | 913 | 816 | 126 | 6.5 | 123.871/200(61.9%) | |||
| 複合文化 | 40 | 948 | 878 | 149 | 5.9 | 110.109/175(62.9%) |
| 年度 | 学部 | 学科 | 専攻など | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 | 合格最低点 |
| 2024 | 教育 | 教育学 | 教育学 生涯教育学 教育心理学 | 95 | 1,008 | 934 | 100 | 7.2 | 95.342/150(63.5%) |
| 1,123 | 1,046 | 76 | 12.6 | 96.675/150(64.4%) | |||||
| 632 | 578 | 57 | 10.1 | 96.251/150(64.1%) | |||||
| 初等教育学 | 20 | 355 | 333 | 30 | 10.4 | 93.554/150(62.3%) | |||
| 国語国文 | 80 | 1,308 | 1,226 | 179 | 5.8 | 104.915/175(59.9%) | |||
| 英語英文 | 80 | 1,379 | 1,269 | 318 | 3.4 | 104.488/175(59.7%) | |||
| 社会 | 地理歴史 公共市民学 | 140 | 1,712 | 1,609 | 207 | 6.1 | 96.865/150(64.5%) | ||
| 1,464 | 1,413 | 255 | 4.6 | 92.292/150(61.5%) | |||||
| 理 | 地球科学 | 20 | 704 | 625 | 86 | 6.5 | 91.782/150(61.1%) | ||
| 数 | 45 | 841 | 757 | 132 | 5.0 | 117.579/200(58.7%) | |||
| 複合文化 | 40 | 924 | 865 | 110 | 5.0 | 110.781/175(63.3%) |
| 年度 | 学部 | 学科 | 専攻など | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 | 合格最低点 |
| 2023 | 教育 | 教育学 | 教育学 生涯教育学 教育心理学 | 95 | 942 | 867 | 112 | 7.7 | 93.682/150(62.4%) |
| 687 | 655 | 114 | 5.7 | 90.002/150(60.0%) | |||||
| 722 | 677 | 64 | 10.6 | 94.023/150(62.6%) | |||||
| 初等教育学 | 20 | 632 | 590 | 40 | 14.8 | 92.795/150(61.8%) | |||
| 国語国文 | 80 | 1,194 | 1,120 | 199 | 5.6 | 106.451/175(60.8%) | |||
| 英語英文 | 80 | 1,642 | 1,520 | 328 | 4.6 | 107.858/175(61.6%) | |||
| 社会 | 地理歴史 公共市民学 | 140 | 1,929 | 1,827 | 217 | 8.4 | 97.546/150(65.0%) | ||
| 1,771 | 1,686 | 248 | 6.8 | 94.899/150(63.2%) | |||||
| 理 | 地球科学 | 20 | 670 | 597 | 94 | 6.4 | 89.272/150(59.5%) | ||
| 数 | 45 | 903 | 806 | 149 | 5.4 | 122.042/200(61.0%) | |||
| 複合文化 | 40 | 1,216 | 1,130 | 129 | 8.8 | 117.045/175(66.8%) |
| 年度 | 学部 | 学科 | 専攻など | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 | 合格最低点 |
| 2022 | 教育 | 教育学 | 教育学 生涯教育学 教育心理学 | 100 | 950 | 889 | 106 | 6.6 | 95.160/150(63.4%) |
| 1,286 | 1,221 | 94 | 11.5 | 96.741/150(64.5%) | |||||
| 691 | 623 | 65 | 8.0 | 95.679/150(63.8%) | |||||
| 初等教育学 | 20 | 444 | 408 | 39 | 10.2 | 93.047/150(62.0%) | |||
| 国語国文 | 80 | 1,389 | 1,312 | 190 | 6.7 | 106.903/175(61.1%) | |||
| 英語英文 | 80 | 2,020 | 1,871 | 340 | 5.1 | 110.163/175(63.0%) | |||
| 社会 | 地理歴史 公共市民学 | 145 | 2,057 | 1,929 | 228 | 6.8 | 97.443/150(65.0%) | ||
| 2,100 | 2,002 | 275 | 6.3 | 96.009/150(64.0%) | |||||
| 理 | 地球科学 | 50(生物学含む) | 678 | 610 | 98 | 5.3 | 86.571/150(57.7%) | ||
| 数 | 45 | 903 | 818 | 178 | 4.6 | 120.000/200(60.0%) | |||
| 複合文化 | 40 | 1,427 | 1,326 | 150 | 6.7 | 114.255/175(65.3%) |
各項目の傾向と対策
大問は全部で4つです。
大問ごとの問題と構成は下の表を参照してください。
| 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | |
| Ⅰ | ・鉄の構造と製造 設問×4 | ・炭素の同素体 設問×4 | ・共有結合の結晶、分子結晶、密度計算 設問×5 |
| Ⅱ | ・合金の性質と用途 設問×6 | ・緩衝液 設問×3 | ・金属のイオン化傾向、電池、水溶液の電気分解、ファラデーの法則 設問×5 |
| Ⅲ | ・堆積物中の有機分子 設問×5 | ・17族元素、13族元素とその化合物 設問×7 | ・16族元素とその化合物 設問×5 |
| Ⅳ | ・温室効果ガス 設問×4 | ・機能性高分子 設問×8 | ・元素分析、アルカン 設問×7 |
理論化学が高い比率で出題されます。
計算問題・数値処理の出題が比較的多く、「結晶格子の計算」が特徴的です。
論述問題などでは、典型的な化学の知識を問う問題ではなく、実際に起きている現象を化学的に考察する問題です。
●対策
まずは教科書や基本レベルの参考書で基礎知識を身につけていきましょう。
公式や解き方の丸暗記や経験による回答ではなく、背景に何があるのかを常に考えながらインプットしていきましょう。
「結晶格子」、「充填率」、「密度」など、無機化学、構造化学の計算問題に特に注意しましょう。
有機化学の構造決定や高分子構造のような問題に対応できるようにするため、実際に手を動かして構造の理解につとめてください。
論述問題や化学反応式を書く問題は各年度で特徴があります。
2025年度は「雨水が石灰岩を長い時間をかけて溶解させる過程を化学反応式で答える問題」、2024年度では「ポリ乳酸がカーボンニュートラルの観点から地球温暖化抑制に寄与する理由を述べる問題」、2023年度では「バイナリー発電の二次流体として、ある有機化合物が使用される理由」など実際の現象を化学的観点で記述する問題が出題されるので、過去問を利用して形式に慣れておきましょう。
全体的に時間が60分しかないので、難易度の判断と計算を素早くやれるように実際に時間を計って演習を積んでいきましょう。
早慶上理対策のまとめはこちら!↓