学習院大学 文学部・コア試験の英語対策
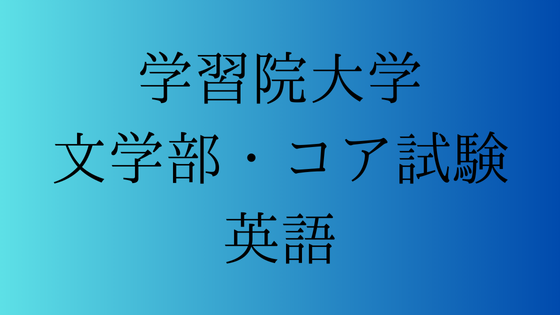
本記事では学習院大学の文学部・コア試験の英語対策について記載しています。
学習院大学はコア試験とプラス試験があり、コア試験が従来通りの学部別の個別試験で、プラス試験は他学部のコア試験で選抜をおこなう試験です。
プラス試験は同一学部を2回受験することができたり、試験日選択の幅ができるなどのメリットがあります。
文学部・コア試験の英語の試験時間は90分で、配点は150点満点です。
目標得点率は80%以上に設定して対策していきましょう。
文学部の入試情報
入学者選抜ガイドをご参照ください。
各項目の傾向と対策
大問は全部で7つです。
大問ごとの問題と構成は下の表を参照してください。
| 2025年度 | 2024年度 | |
| Ⅰ | ・長文読解(40点) A. 下線部の言い換え B. 下線部の意味 C. 空所補充問題 D. 和訳問題 E. 下線部の動詞を直す F. 下線部の意味 G. 空所補充問題 H. 下線部の意味 I. 下線部の意味 J.下線部の整序問題 K. 内容一致(2つ) | ・長文読解(40点) A. 下線部の意味 B. 空所補充問題 C. 下線部の言い換え D. 下線部の理由 E. 空所補充問題 F. 下線部の説明 G. 下線部の意味 H. 和訳問題 I. 下線部の言い換え J. 内容一致(2つ) |
| Ⅱ | ・長文読解(40点) A. 下線部が明らかにした内容 B. 下線部の言い換え C. 下線部の具体例 D. 和訳問題 E. 空所補充問題 F. 空所補充問題 G. 下線部の言い換え H. 下線部の言い換え I. 下線部の整序問題 J.内容一致(2つ) | ・長文読解(40点) A. 抜き出し問題 B. 和訳問題 C. 下線部が指す内容 D. 下線部の意味 E. 語句の整序問題 F. 下線部の意味 G. 下線部の意味 H. 空所補充問題 I. 下線部が指す内容 J. 内容一致(2つ) |
| Ⅲ | ・長文の空所補充(15点) 空所補充問題×5 | ・長文の空所補充(15点) 空所補充問題×5 |
| Ⅳ | ・文法、語法、熟語問題(15点) 空所補充問題×5 | ・文法、語法、熟語問題(15点) 空所補充問題×5 |
| Ⅴ | ・文法、語法、熟語問題(15点) 正誤問題×5 | ・文法、語法、熟語問題(15点) 正誤問題×5 |
| Ⅵ | ・会話問題(15点) 空所補充問題×5 | ・会話問題(15点) 空所補充問題×5 |
| Ⅶ | ・和文英訳問題(10点) 空所補充問題×2 | ・和文英訳問題(10点) 空所補充問題×2 |
| 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |
| Ⅰ | ・長文読解 A:下線部が指す内容 B:下線部の意味に最も近いもの C:下線部が指すもの D:空所補充問題 E:下線部の言い換え F:和訳問題 G:下線部の言い換え H:下線部の意味に最も近いもの I:空所補充問題 J:下線部の理由 K:内容一致(2つ) | ・長文読解 A:下線部が指すもの B:文章中の整序問題 C:下線部の意味に最も近いもの D:下線部の意味に最も近いもの E:空所補充問題 F:下線部の意味に最も近いもの G:下線部の言い換え H:下線部の意味に最も近いもの I:和訳問題 J:内容一致(2つ) | ・長文読解 A:下線部の結果にあてはまらないこと B:空所補充問題 C:下線部が伝えようとしていること D:下線部が指すもの E:空所補充問題(入らないもの) F:和訳問題 G:下線部の理由 H:下線部の例 I:文章中の整序問題 J:下線部の理由 K:内容一致(2つ) |
| Ⅱ | ・長文読解 A:下線部の意味に最も近いもの B:下線部が指すもの C:下線部が指すもの D:下線部が指すもの E:空所補充問題 F:下線部の言い換え G:和訳問題 H:下線部と同じ意味を指すもの(抜き出し) I:内容一致(2つ) | ・長文読解 A:空所補充問題 B:下線部が指すもの C:下線部が指す意味内容 D:空所補充問題 E:下線部の用法に近いもの F:和訳問題 G:下線部の言い換え H:下線部の言い換え I:下線部の意味に最も近いもの J:内容一致(2つ) | ・長文読解 A:下線部が指すもの B:下線部の意味に最も近いもの C:下線部の意味に最も近いもの D:文章中の整序問題 E:下線部の意味に最も近いもの F:下線部の意味に最も近いもの G:下線部の理由 H:和訳問題 I:下線部の内容の説明 J:下線部の内容の説明 K:内容一致(2つ) |
| Ⅲ | 空所補充問題×5 | 空所補充問題×5 | 空所補充問題×5 |
| Ⅳ | 文法・語法・熟語問題×5 | 文法・語法・熟語問題×5 | 文法・語法・熟語問題×5 |
| Ⅴ | 正誤問題×5 | 正誤問題×5 | 正誤問題×5 |
| Ⅵ | 会話問題×5 | 会話問題×5 | 会話問題×5 |
| Ⅶ | 英訳問題(空所補充)×2 | 英訳問題(空所補充)×2 | 英訳問題(空所補充)×2 |
表にあるとおり、長文読解が2題、文章中の空所補充問題、文法・語法・熟語問題、正誤問題、会話問題、英訳問題という構成です。
問題のレベルは基本~標準レベルですが、種類が多いので対策に時間がかかります。
『ネクステージ』などの標準的な網羅系問題集を利用しつつ、単語、熟語暗記と英文解釈、長文読解に力を入れて対策していきましょう。
●長文読解(大問1,2)
表にあるとおり多様な問題が出題されますが、下線部やその前後関係を読み取ることができているのかを確認する問題ということで共通しています。
下線部や空所の内容や前後を確認し、「どういうことを言っているのか」を言語化できるように、普段から長文読解の演習を積んでいきましょう。
和訳問題も出題されるので、基本的な単語や文法をおさえたら英文解釈に時間をかけてください。
内容一致問題は選択肢が7つあるうち、2つを選ぶ問題です。文章を読みながら段落ごとに内容をメモしておくと参照しやすいです。
●空所補充問題(大問3)
文章中の文脈に合うように語句を空所に入れていく問題です。
基本的には意味を考えて回答しますが、文法問題の要素もあります。
選択肢を見る前に、ある程度意味を推測し、その後選択肢を検討していきましょう。
●文法・語法・熟語問題(大問4)
文法、語法、熟語の空所補充問題です。
『ネクステージ』などの網羅系問題集をつかって文法事項の理解、語法、熟語の暗記に力をいれましょう。
●正誤問題(大問5)
正誤問題は苦手とする人が多いです。
文法知識を丸暗記するのではなく、理解するようにしましょう。
学習院大学ではどの学部も正誤問題を出題するので、できる限りたくさん解くようにしましょう。
●会話問題(大問6)
英検の単語集や『ネクステージ』などの網羅系の問題集などを使って会話表現を覚えていきましょう。
●英訳問題(大問7)
日本語が書かれており、それをもとにした英文を作成します。
全文を作成するのではなく、空所があるので適語をいれていきます。
文法だけでなく語法、熟語表現のアウトプットを必要とします。
他学部でも同様の問題が出されるので、数多く解いて形式に慣れるようにしましょう。
GMARCH対策のまとめはこちら!
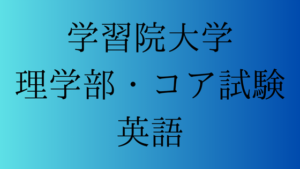
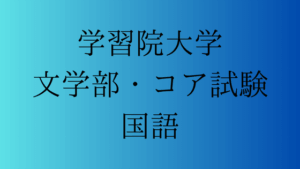
“学習院大学 文学部・コア試験の英語対策” に対して1件のコメントがあります。
コメントは受け付けていません。