青山学院大学 教育人間科学部・教育学科の小論文対策
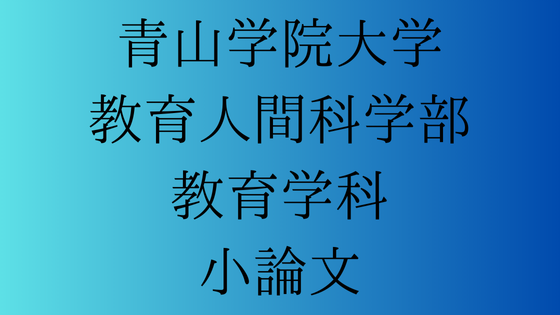
本記事では青山学院大学 教育人間科学部 教育学科の小論文対策について記載しています。
教育人間科学部 教育学科は共通テストと独自問題(小論文)の点数で合否判定をします。
共通テストの配点は英語(リーディング・リスニング)が100点、国語が100点であり、基準点が設けられています。基準点に達していない場合、小論文は採点されません。
小論文の配点は100点で、試験時間は90分です。
教育人間科学部教育学科の情報(個別日程)
| 年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 | 合格最低 点/満点 |
| 2025 | 約20 | 357 | 329 | 70 | 4.7 | 共通テストの「英語」、「国語」を50%圧縮した合計点が140.0点以上かつ「小論文」の点数が60.0点以上 |
| 2024 | 約20 | 476 | 437 | 65 | 6.7 | 共通テストの「英語」、「国語」を50%圧縮した合計点が130.0点以上かつ「小論文」の点数が69.0点以上 |
| 2023 | 約20 | 379 | 352 | 63 | 5.6 | 共通テストの「英語」、「国語」を50%圧縮した合計点が125.0点以上かつ「小論文」の点数が57.0点以上 |
| 2022 | 約20 | 439 | 404 | 76 | 5.3 | 共通テストの「英語」、「国語」を50%圧縮した合計点が127.5点以上かつ「小論文」の点数が56点以上 |
| 2021 | 約20 | 335 | 297 | 113 | 2.6 | 共通テストの「英語」、「国語」を50%圧縮した合計点が117点以上かつ「小論文」の点数が40点以上 |
●全体の傾向
大問は2つあり、小論文の形式は資料参照型と文章参照型です。
大問1はグラフや表などの資料をもとに考察する問題で、大問2は文章を読んで要約、意見を述べる問題です。
●年度別の出題内容
| 出題年度 | 内容 |
| 2024年度 | ・大問1 中学校の教員1日当たりの業務時間の内訳(200字以内)、大学生1人当たりが年間に支出する学費および生活費を大学(昼間部)の設置者別に示したもの(表1)と学生の居住形態の違いを大学(昼間部)の設置者別に割合で示したもの(表2)(300字以内考察) ・大問2 『近代科学を超えて』村上陽一郎 著から出題(200字以内要約、600字以内で意見を論述) |
| 2023年度 | ・大問1 「今後1年間、あなたはどのようなことを食育として実践したいと思いますか」という質問に対する回答結果の傾向(200字以内説明)、学校数の推移と在学者数の推移に関する図(300字以内考察) ・大問2 『現代思想の冒険』竹田青嗣 著から出題(200字以内要約、600字以内で意見を論述) |
| 2022年度 | ・大問1 各国の高齢化率の推移(200字以内考察)、保護者が子どもと一緒に図書館に行く頻度と子どもの学力との関係を表わした表、家庭の蔵書量と子どもの学力との関係を表わした表(300字以内考察) ・大問2 『栽培植物と農耕の起源』中尾佐助 著から出題(200字以内要約、600字以内で意見を論述) |
| 2021年度 | ・大問1 新刊書籍の出版点数と書籍の販売部数の図(200字以内考察)、青少年のインターネット上の経験に関する調査結果(300字以内考察) ・大問2 『現代論理学入門』沢田允茂 著から出題(200字以内要約、600字以内で意見を論述) |
●問題別の分析
大問1のグラフ、表は考察しにくいものではなく特徴がわかりやすいので、比較的書くのは簡単です。素直に読み取れたことを200字、300字以内で論述していけば得点できます。
具体的な数字を用いて誰が読んでもわかりやすい構成を心がけましょう。
大問2の1問目は文章量に対して指定字数が少ないので、過去問をつかって徹底的に練習していないと大きな失点につながります。
段落ごとに内容をまとめていき、最終的に著者は何を伝えたいのかを明確にし、それを端的に要約していきます。
具体例など要約するときに余計な情報は思い切って削ってしまう潔さも必要です。
段落を上から箇条書きのようにまとめていくと字数が足りなくなりますので、とにかく著者の言いたいことを抽象化していくというプロセスが必要です。
過去問だけでなく、他大学、他学部の現代文の問題も練習に使うことができます。
「つまり何を言いたいのか」という点を念頭に置いて考え抜く習慣が身につくと国語力自体があがり、要約や意見を述べるときに効果を発揮します。
要約がスムーズにできれば、2問目の「背景や意義に触れつつ、複数の具体例を挙げながら自分の考えを述べる問題」も悩まずに書き出せます。
小論文を書いた後には学校の先生や予備校、塾の講師に添削をしてもらってください。
また、演習の段階では一度書き切ったあとに、添削をもとに何度も推敲して論述力を高めていきましょう。
青山学院大学 教育人間科学部 心理学科の小論文対策はこちらです。
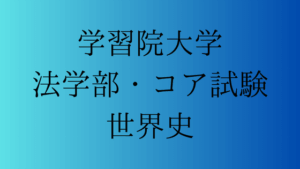
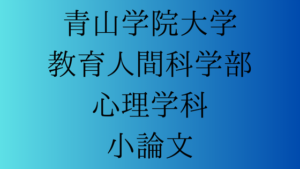
“青山学院大学 教育人間科学部・教育学科の小論文対策” に対して2件のコメントがあります。
コメントは受け付けていません。