2020年度以降に大学受験する人がリスニングを鍛えるべき理由と対策
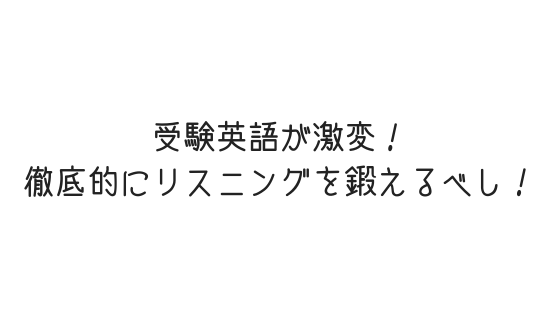
ご存知の方が多いとおもいますが、2020年1月を最後にセンター試験が廃止され、2021年1月より大学入学共通テストに変わる予定です。
全教科について出題の仕方が変わりますが、なかでも英語は大きく変化します。
今まで筆記とリスニングという形で点数が決まっていましたが、2021年より筆記とリスニングに加え、資格・検定試験も評価されます。
世界はとっくにグローバル化されており、世の中の動きに対応するために学習内容についても変える必要があると判断されたためです。
現在は筆記が200点満点、リスニングは50点満点ですが、大学入試共通テストでは筆記とリスニングの配点が各100点になります。
つまり今まで単語と文法をつめこみ何となくでも文章が読めれば、それなりに点数を取れていた英語が、リスニング能力も視野にいれて対策しないと点を取れない教科に変わるということです。
しかし、恐れる必要はありません。
リスニングの勉強法自体はしっかり確立されたものがあります。
本記事ではリスニングの対策方法についてお伝えします。
単語を正しく発音できるようにしよう
ハッキリ言いましょう。
自分で正しく発音できない単語は聞き取ることができません。
あまりリスニングの勉強をしたことがない人にとっては信じられないことかもしれませんが、これは本当のことです。
試験では「これはリンゴです」は”This is an apple”と発音され、“ディス イズ アン アップル”とは言ってくれないということです。
事実として、だいたいの日本人は恥ずかしがって発音記号通りに発音しません。
無意識に「英語は特別な言語だ」という思いがあるので、ちゃんと発音することがなんとなく恥ずかしく感じるし、ちゃんと発音している人を「気取っている」と感じてしまうのです。
ただ、日本は島国で国内どこにいっても日本語が通じてしまうため、英語を使うということが身近ではありません。
特別な言語と認識してしまうのも無理のないことです。
しかし、それではまったくリスニング能力が上がりません。
恥ずかしくてもなんでもCDを聴いたり、発音記号を理解したりして正しい発音ができるようになるまで練習しましょう。
方法① ディクテーション
単語を正しく発音できるようになったら、本格的にリスニングの対策をしましょう。
まずはディクテーションという方法をお教えします。
ディクテーションとは読み上げられた英語をそのまま書き取ることを指します。
単語ではなく文章単位で紙などに書き取っていくことで、あいまいに聞き取るということを防ぐことができるようになります。
ディクテーションの具体的な手順は下記の通り。
❶ CDなどから読み上げられる音声を聴く
❷ 聞こえてきたまま英文を書きとっていく
❸ スクリプト(原稿)をみながら聞き取れなかったところを加筆・修正していく
❹ スクリプトをみて完成された文をみながらもう一度聴いてみる
以上の手順をたくさんの文で行います。
いきなり長い文量のテキストを使わないことが継続のコツです。
ディクテーションは想像以上にしんどい作業になりますので、比較的短くやさしい文章にしましょう。
あらゆる教材の中でもセンター試験のリスニング問題がディクテーションに適していると思います。
多くの問題がありますし、練習量としては申し分ないです。
方法② シャドウイング
次はシャドウイングという練習方法をお教えします。
シャドウイングとは英語を聴きながらそれをそのまま真似して読み上げるという練習方法です。
通訳訓練としても実施されているリスニングの練習方法なので確実に効果があります。
英語のプロになろうとしている人たちがやっている練習なので効果があるのは明白ですよね。
シャドウイングの具体的な手順は下記の通り。
❶ シャドウイングせずに一度文章を最後まで聴いてみる
❷ 流れてきた文章をあとに続いて発音していく
❸ スクリプトをみて発音できなかった部分をチェックする
❹ 全文を把握したらもう一度シャドウイングをする
ディクテーションと同じように以上の手順でいくつかの文章をつかって練習していきましょう。
教材についてもディクテーションと同じく、センター試験のリスニング問題が適しています。
ちなみにですが、洋画1本のシャドウイングをやりきったら、おそらく受験で出題されるリスニングについては無敵になりますので、興味がある人は挑戦してみてください。
まとめ
2020年度入試の英語激変にそなえてやるべきことは…
・リスニングを徹底的に強化すること!
・ディクテーションかシャドウイング(両方でも可)で練習すること!
本記事で紹介した勉強法は受験だけでなく他の英語資格試験でも通用する方法ですので、ぜひ試してみてください。
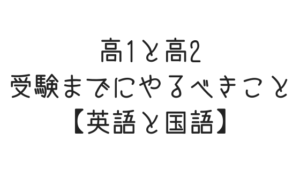
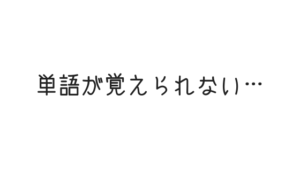
“2020年度以降に大学受験する人がリスニングを鍛えるべき理由と対策” に対して2件のコメントがあります。