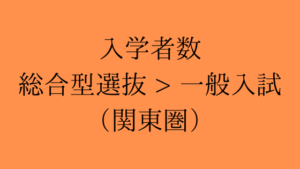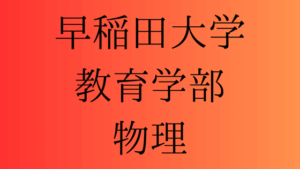入学方式の変遷(一般入試、推薦入試、総合型選抜(AO入試))
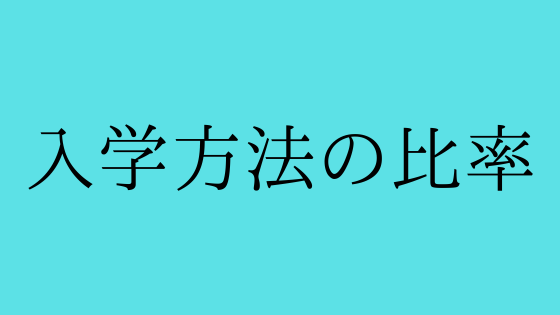
国立大学、公立大学、私立大学のそれぞれの入学方式が変化してきています。
代表的な入学方式は一般入試、推薦入試、総合型選抜(AO入試)ですが、一般入試以外の入試形式の割合が増えてきており、特に私立大学では顕著です。
本記事では具体的にそれぞれの比率がどうなっているのかについて記載しています。
2000年と2025年の比較
一般入試、推薦入試、総合型選抜(2000年時はAO入試)での入学者数は2000年(平成12年)と比較してどのように変わってきたのかを国立大学、公立大学、私立大学別にご紹介します。
●国立大学
・2000年
| 一般入試 | 84.6% |
| 推薦入試 | 12.1% |
| AO入試 | 2.7% |
| その他 | 0.5% |
・2025年
| 一般入試 | 79.7% |
| 推薦入試 | 12.6% |
| 総合型選抜 | 6.5% |
| その他 | 1.2% |
●公立大学
・2000年
| 一般入試 | 73.2% |
| 推薦入試 | 24.0% |
| AO入試 | 2.2% |
| その他 | 0.7% |
・2025年
| 一般入試 | 67.4% |
| 推薦入試 | 26.7% |
| 総合型選抜 | 5.1% |
| その他 | 0.8% |
●私立大学
・2000年
| 一般入試 | 49.0% |
| 推薦入試 | 40.1% |
| AO入試 | 10.5% |
| その他 | 0.4% |
・2025年
| 一般入試 | 37.5% |
| 推薦入試 | 38.4% |
| 総合型選抜 | 19.4% |
| その他 | 4.7% |
以上のデータは文部科学省の「(3)大学入学者選抜に関する資料」、『2026年度用大学の真の実力情報公開BOOK』を出典としています。
一般入試の割合が一番高い国立大学でも、2025年にはその割合は8割を切り、総合型選抜での入学者が増えています。
2000年にAO入試を他の国立大学よりも早く導入した東北大学は2050年までに全ての入試を総合型選抜に移行する構想があるように、一般入試の入学者割合は徐々に減っていくと考えられます。
私立大学は2000年の時点で一般入試以外での入学者が過半数ですが、2025年はさらに増えており、一般入試以外での入学者は6割以上になっています。
推薦入試には「公募制」、「指定校制」、「付属校・系列校」があり、その比率は下記の通りになっています。(2025年度のデータ、『2026年度用大学の真の実力情報公開BOOK』参照)
| 公募制 | 23.7% |
| 指定校制 | 59.0% |
| 付属校・系列校 | 17.3% |
推薦入試の大半を指定校制が占めています。
付属校・系列校での入学もあるので、高校入試の時点で受験勉強が苦手だと感じている中学生は将来のことを考えて、付属・系列の私立高校に入学するのも一手です。
一般入試で入学したらすごいということや、ベースの学力があるということではなく、大学入学後の進級、卒業や充実度は目的意識が大きく関わっています。
入試方式が一般入試、推薦入試、総合型選抜のどれであっても、偏差値で選んだり、両親や友達などの周囲の人に言われたまま入学したといった外的理由で進学すると、ぼんやり4~6年を過ごす可能性が高いです。
上記の方式は基本的に得意か不得意かで選択しましょう。
1年以上の勉強をしてテストで結果を出す方式が得意であれば一般入試、約3年間の定期テストで決められた範囲のものを短期間で勉強することが得意であれば推薦入試、事前に資料などを作成したり面接で話すことが得意であれば総合型選抜のように、自身の適正を考えて入試方式を考えていきましょう。