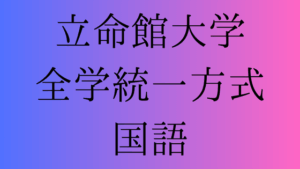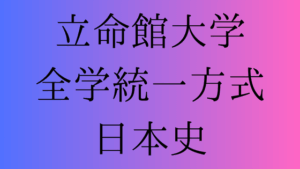東京科学大学(前期日程)の化学対策
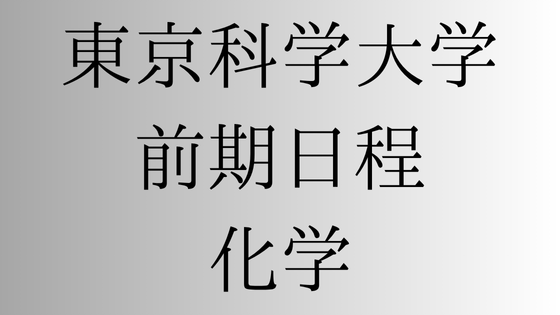
本記事では東京科学大学(前期日程)の化学対策について記載しています。
*2024年10月より東京工業大学は東京医科歯科大学と統合して「東京科学大学」に名称変更されています。
東京科学大学は共通テストの点数が足きりにのみ利用され、合否は二次試験の点数で決まります。
東京科学大学の化学の試験時間は120分で、配点は150点満点です。(化学と物理を合わせて300点です)
統合後の医学部と歯学部の化学は120点満点です。医学部、歯学部の問題とは異なるのでご注意ください。
目標得点率は65%程度に設定して勉強していきましょう。
東京科学大学の入試情報
東京科学大学の公式サイトをご参照ください。
各項目の傾向と対策
大問は全部で3つです。
大問ごとの問題と構成は下の表を参照してください。
| 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | |
| 1 | ・金属元素の性質、いろいろな物質の性質、電池・電気分解、電離定数とpHの計算、結晶格子(50点) 設問×7 | ・周期表と元素の性質、金属元素の性質、水溶液の電気分解、電離平衡・塩の加水分解、結晶構造(50点) 設問×8 | ・いろいろな元素の性質、金属元素の性質、電気分解、溶解度積、イオン結晶(50点) 設問×7 |
| 2 | ・いろいろな物質の性質、希薄溶液、化学平衡、混合気体の圧力、エンタルピー変化(50点) 設問×7 | ・化学結合、反応速度、反応熱、凝固点降下・浸透圧、混合気体の反応・蒸気圧(50点) 設問×5 | ・状態図、反応速度・化学平衡、気体、気体の溶解平衡、熱化学(50点) 設問×6 |
| 3 | ・芳香族化合物、脂肪族化合物、糖類、ペプチド、構造決定(50点) 設問×5 | ・C5H12Oの異性体、エステルの構造決定、糖類、タンパク質、芳香族化合物の構造決定(50点) 設問×5 | ・芳香族炭化水素、カルボン酸、トリペプチド、合成高分子、構造決定(50点) 設問×5 |
大問は3つですが、中問がテーマ別に5題前後あり、全体で15問前後という構成になっています。
計算で数値を求める問題で途中過程を記述する必要はなく、答えのみを記述する問題が出題されます。
化学結合や元素の周期律、分子の構造や極性に関する問題は比較的標準的なレベルであることが多いです。
方程式を立てる際に何を文字で置いて立式できるかがポイントです。
●対策
・物質の構造
電子親和力、電気陰性度、イオン化エネルギー、分子の構造、極性については、それぞれの厳密な定義や電気双極子のモーメントは何かなど発展的な内容も理解しておきましょう。
結晶構造についての問題は図を描いて、空間的な位置把握を意識しましょう。
化学反応の量的関係についての問題は出題文をよく読んで、何を求めるべきなのかを把握する練習を積んでいきましょう。
・物質の状態、状態変化
物質の三態変化について、状態図や温度とエネルギーの関係を表すグラフなどを自然現象などと結びつけて学習していきましょう。
混合気体や蒸気圧、希薄溶液の性質などは背後にある理由や問題点などについて教科書レベルを超えた理解をしておきましょう。
・物質の化学変化
熱化学はエネルギー図を素早く描けるように練習しておきましょう。
中和滴定を利用した炭酸ナトリウムの2段階滴定やアンモニアの逆滴定、CODやI2を用いた酸化還元滴定などの計算問題の練習を多く積んでおきましょう。
電気分解では、電池などを直列、または並列に接続した場合の計算問題の練習を積んでおきましょう。
平衡移動の原理を用いた計算問題は頻出です。
・無機物質
単体、化合物に関する問題、金属イオンの反応や気体の製法、無機化学工業など無機化学全体から出題され、理論化学と関連した問題が多いです。
・有機化合物
脂肪族・芳香族化合物の性質や合成法、異性体などに関しては、ほとんど基本〜標準レベルです。
ザイツェフ則などの教科書の範囲を超えた内容も確認しておきましょう。
・天然有機化合物、合成高分子化合物
天然有機化合物の糖類、アミノ酸、タンパク質から合成高分子化合物まで幅広く出題されています。
生態高分子化合物のDNAやRNAに関する設問はほとんど出題されていません。
ポリマーに関する計算問題や重合体における単量体の割合を問う問題など難易度の高い問題も出題されていますが、全体的に標準レベルです。
難関国立大学対策のまとめはこちら!↓