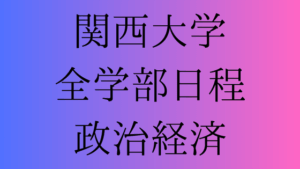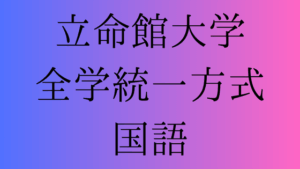東京科学大学(前期日程)の数学対策
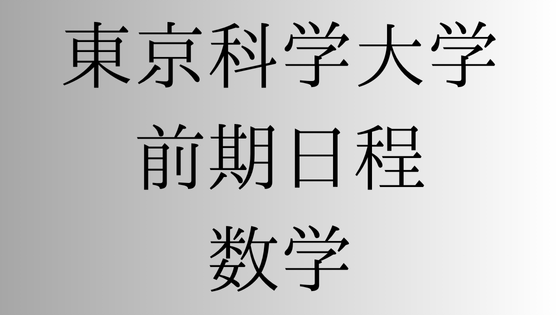
本記事では東京科学大学(前期日程)の数学対策について記載しています。
*2024年10月より東京工業大学は東京医科歯科大学と統合して「東京科学大学」に名称変更されています。
東京科学大学は共通テストの点数が足きりにのみ利用され、合否は二次試験の点数で決まります。
東京科学大学の数学の試験時間は180分で、配点は300点満点です。
統合後の医学部と歯学部の数学は120点満点です。医学部、歯学部の問題とは異なるのでご注意ください。
目標得点率は65%程度に設定して勉強していきましょう。
東京科学大学の入試情報
東京科学大学の公式サイトをご参照ください。
各項目の傾向と対策
大問は全部で5つです。
大問ごとの問題と構成は下の表を参照してください。
| 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | |
| 1 | ・微積分(60点) 設問×3 | ・円と直線(円と曲線)、曲線の媒介変数表示(60点) 設問×2 | ・定積分と不等式(60点) 設問×1 |
| 2 | ・ベクトル(60点) 設問×3 | ・導関数、曲線の媒介変数表示、曲線の長さ(60点) 設問×4 | ・不定方程式(60点) 設問×1 |
| 3 | ・確率、極限(60点) 設問×4 | ・漸化式、数列の極限(60点) 設問×3 | ・複素数の極形式、確率と漸化式、独立・反復試行の確率(60点) 設問×2 |
| 4 | ・三角関数、数列(60点) 設問×3 | ・確率と漸化式、数列と極限(60点) 設問×3 | ・体積(60点) 設問×1 |
| 5 | ・微分法の応用、極限(60点) 設問×2 | ・ド・モアブルの定理、解と係数の関係(60点) 設問×1 | ・平面の方程式、空間ベクトルの内積(60点) 設問×2 |
微積分、確率、極限に大きな比重が置かれています。中でも微積分法は頻出です。
頻出分野はあくまで頻出なだけであって、他の分野からは出題されないということはないので、なかなか傾向が読めないという特徴も相まって、満遍なく勉強する必要があります。
整数問題や平面・空間図形の計量問題が出題されたときは難問であることが多いので、最初の問題選定で、解かない問題や部分点を狙う問題に設定していくことも戦略の一つです。
東京工業大学時代から続く、「問題文が短い」という特徴は2025年度入試でも変化がありません。短いということは問題を解く際のヒントが少ないということなので、ほとんど自力で解き切る必要がある点も難易度が高いポイントです。
全体的に計算力を必要とする問題が多いので、考え方だけを鍛えるのではなく、地道な計算もしっかりやっておく必要があります。
●対策
まずは教科書に記載されている公式などの理解度をあげていきましょう。
各公式の証明ができることは前提として、違った視点も必要です。
演習に早く入れるように数学ⅢCの学習は高校3年生までに終えておきましょう。
教科書レベルの知識への解像度をあげるためには、多くの問題を解くことが必要です。
最初から公式の証明まで注目しておくことは重要である一方、出口がわかっていない中で公式の導出方法をマスターしても問題に応用することが難しい可能性があります。
『青チャート』などの網羅系の問題集や『一対一対応の数学』シリーズのような発展的な解法が記載されている問題集で典型的な問題を解けるようになった後は、『理系数学の良問プラチカ』や『やさしい理系数学』などの応用的な問題集に入ってもいいですし、『東工大の数学20ヵ年』のような東工大の問題が数多く記載されている問題集をやってみてもいいでしょう。
解き方を身につけると同時に、記述式の回答方法を鍛えていく必要があります。
解法を思い浮かんだからOKということではなく、最初から最後まで走り切れるのかも確認する必要があります。
計算力に不安がある場合は『合格る計算』シリーズなどを使って計算練習を積んでおきましょう。
東京科学大学の数学は1題あたりに時間を長くかけられるので、難易度の高い問題について時間をかけて考え抜く練習も効果的です。
難関国立大学対策のまとめはこちら!↓