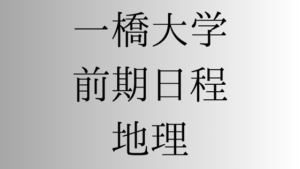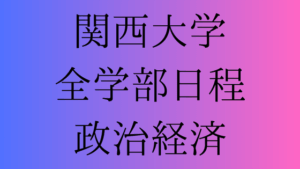東京科学大学(前期日程)の物理対策
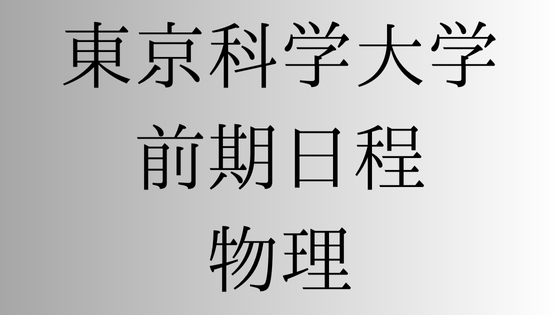
本記事では東京科学大学(前期日程)の物理対策について記載しています。
*2024年10月より東京工業大学は東京医科歯科大学と統合して「東京科学大学」に名称変更されています。
東京科学大学は共通テストの点数が足きりにのみ利用され、合否は二次試験の点数で決まります。
東京科学大学の物理の試験時間は120分で、配点は150点満点です。(化学と物理を合わせて300点です)
統合後の医学部と歯学部の物理は120点満点です。医学部、歯学部の問題とは異なるのでご注意ください。
目標得点率は65%程度に設定して勉強していきましょう。
東京科学大学の入試情報
東京科学大学の公式サイトをご参照ください。
各項目の傾向と対策
大問は全部で3つです。
大問ごとの問題と構成は下の表を参照してください。
| 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | |
| 1 | ・回転する円錐内面上の物体(50点) 設問×9 | ・静力学、振り子(50点) 設問×10 | ・あらい床でのバネによる運動、放物運動、衝突、断熱変化によるピストンの単振動(50点) 設問×9 |
| 2 | ・コンデンサー間の導体が受ける力(50点) 設問×7 | ・電磁誘導、抵抗、電池、コイル(50点) 設問×7 | ・ダイオードの特性を用いた電気回路、導体棒の運動による電磁誘導(50点) 設問×8 |
| 3 | ・断熱変化とジュール・トムソン効果(50点) 設問×8 | ・定圧変化、等温変化、断熱変化(50点) 設問×8 | ・X線回折による結晶構造分析、電子線屈折と干渉(50点) 設問×8 |
大問数は3問ですが、4問出題された年度もあります。
力学と電磁気学は毎年出題されています。
公式を覚えているだけで解ける問題はほとんど出題されません。
物理的な現象を見てどれだけ解像度高く理解できるか、そしてそれに対して満足いく回答を用意できるかが問われます。
波動の分野では電磁波の干渉、光の音波による反射、電磁気の分野では非慣性系から見た電磁場の強さ、非常に高度な内容を扱っていることがあります。
力学と電磁気、電磁気と熱力学、波動と熱力学の融合問題なども出題されます。
基本的に導出の過程も記述する問題が多く、証明・論述問題、グラフを描く問題も出題されています。
●対策
導出過程を書かせる問題が出題されるので、物理的現象を観察して適切に回答していく必要があります。
日頃の学習から空所補充問題であっても、その導出の過程や考え方を言語化する練習が必要です。
物理用語や公式の意味を正確に把握しておきましょう。
力学は保存則の適用、単振動、摩擦力、電磁気はコンデンサーの基礎理論、電磁誘導、電磁場内の荷電粒子の運動、熱力学は断熱変化などの気体の状態変化、波動は波の式、干渉、原子は光電効果、物質波の干渉が重要分野です。
教科書、参考書、セミナーなどで基礎知識を身につけた後、『物理のエッセンス』などを使って問題演習を積んでいきましょう。
その後は『重要問題集』や『名問の森』などの問題集で応用問題の演習を積んでいきましょう。
物理を得点源にしたい人は『難問題の系統とその解き方』などを使って、さらに応用問題の演習を積んでいきます。
ある程度勉強し終えたら、『東工大の物理20ヵ年』や過去問を使って、得点力をつけていきます。
計算量も多いので、解法がわかったからいいとはならずに、最初から最後まで書き切れるのかを重視して勉強していきましょう。
難関国立大学対策のまとめはこちら!↓