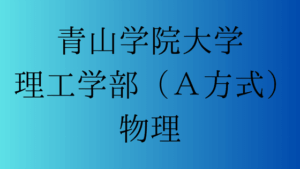青山学院大学 理工学部(A方式)の数学対策
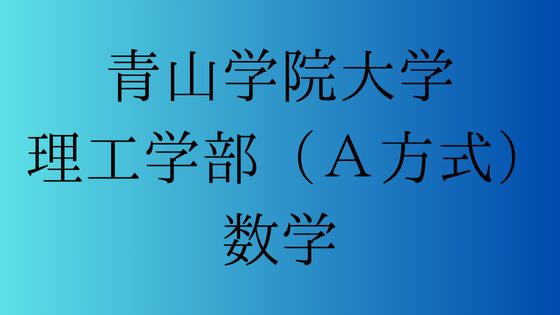
本記事では青山学院大学 理工学部(A方式)の数学対策について記載しています。
理工学部の数学の試験時間は100分で、配点は150点です。
目標得点率は70%以上に設定して勉強しましょう。
理工学部(A方式)の情報
| 学科 | 年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 | 合格最低点/満点 |
| 物理科 | 2025 | 約35 | 475 | 446 | 111 | 4.0 | 303.0/450.0(67.3%) |
| 2024 | 約35 | 550 | 526 | 156 | 3.4 | 298.0/450.0(66.2%) | |
| 2023 | 約35 | 471 | 450 | 215 | 2.1 | 255.0/450.0(57%) | |
| 2022 | 約35 | 762 | 723 | 190 | 3.8 | 278.0/450.0(62%) | |
| 2021 | 約35 | 528 | 499 | 218 | 2.3 | 261.0/450.0(58%) | |
| 数理サイエンス | 2025 | 約20 | 298 | 285 | 89 | 3.2 | 276.0/450.0(61.3%) |
| 2024 | 約20 | 285 | 270 | 94 | 2.9 | 261.0/450.0(58.0%) | |
| 2023 | 約20 | 350 | 331 | 121 | 2.7 | 257.0/450.0(57%) | |
| 2022 | 約20 | 288 | 271 | 122 | 2.2 | 252.0/450.0(56%) | |
| 2021 | 約20 | 311 | 301 | 112 | 2.7 | 263.0/450.0(58%) | |
| 化学・生命科 | 2025 | 約50 | 837 | 783 | 252 | 3.1 | 278.0/450.0(61.8%) |
| 2024 | 約50 | 782 | 750 | 267 | 2.8 | 263.9/450.0(58.4%) | |
| 2023 | 約50 | 808 | 765 | 307 | 2.5 | 261.0/450.0(58%) | |
| 2022 | 約50 | 836 | 795 | 348 | 2.3 | 250.0/450.0(56%) | |
| 2021 | 約50 | 702 | 670 | 313 | 2.1 | 247.0/450.0(55%) | |
| 電気電子工 | 2025 | 約40 | 483 | 460 | 145 | 3.2 | 258.0/450.0(57.3%) |
| 2024 | 約40 | 492 | 471 | 151 | 3.1 | 262.0/450.0(58.2%) | |
| 2023 | 約40 | 479 | 457 | 155 | 2.9 | 261.0/450.0(58%) | |
| 2022 | 約40 | 608 | 579 | 177 | 3.3 | 267.0/450.0(59%) | |
| 2021 | 約40 | 518 | 495 | 172 | 2.9 | 268.0/450.0(60%) | |
| 機械創造工 | 2025 | 約40 | 723 | 693 | 204 | 3.4 | 271.0/450.0(60.2%) |
| 2024 | 約40 | 699 | 668 | 271 | 2.5 | 261.0/450.0(58.0%) | |
| 2023 | 約40 | 973 | 936 | 272 | 3.4 | 264.0/450.0(59%) | |
| 2022 | 約40 | 749 | 717 | 299 | 2.4 | 252.0/450.0(56%) | |
| 2021 | 約40 | 528 | 505 | 301 | 1.7 | 241.0/450.0(54%) | |
| 経営システム工 | 2025 | 約35 | 510 | 483 | 169 | 2.9 | 266.0/450.0(59.1%) |
| 2024 | 約35 | 519 | 504 | 173 | 2.9 | 276.0/450.0(61.3%) | |
| 2023 | 約35 | 560 | 534 | 172 | 3.1 | 265.0/450.0(59%) | |
| 2022 | 約35 | 649 | 620 | 207 | 3.0 | 273.0/450.0(61%) | |
| 2021 | 約35 | 571 | 545 | 196 | 2.8 | 275.0/450.0(61%) | |
| 情報テクノロジー | 2025 | 約35 | 676 | 642 | 160 | 4.0 | 288.0/450.0(64.0%) |
| 2024 | 約35 | 672 | 618 | 174 | 3.6 | 275.0/450.0(61.1%) | |
| 2023 | 約35 | 810 | 760 | 195 | 3.9 | 278.0/450.0(62%) | |
| 2022 | 約35 | 769 | 717 | 177 | 4.1 | 280.0/450.0(62%) | |
| 2021 | 約35 | 762 | 724 | 146 | 5.0 | 302.0/450.0(67%) |
各項目の傾向と対策
大問は全部で5つです。
下の表で出題される問題を確認しましょう。
| 2025年度 | 2024年度 | |
| 1 | ・独立・反復試行の確率(数学A) 設問×3 | ・確率の基本性質(数学A) 設問×4 |
| 2 | ・複素数の方程式(数学C) 設問×2 | ・面積、体積(数学Ⅱ) 設問×3 |
| 3 | ・三角関数の微積分(数学Ⅲ) 設問×3 | ・解と係数の関係、領域の最大・最小(数学Ⅱ) 設問×2 |
| 4 | ・平面図形と軌跡(数学Ⅱ) 設問×3 | ・漸化式(数学B) 設問×4 |
| 5 | ・ベクトルと図形(平面)(数学C) 設問×3 | ・曲線の凹凸・変曲点、体積(数学Ⅲ) 設問×3 |
| 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |
| 1 | ・ベクトルと図形(空間)(数学B) 設問×4 | ・確率の基本性質(数学A) 設問×4 | ・確率の基本性質(数学A) 設問×3 |
| 2 | ・独立・反復試行の確率、条件つき確率(数学A) 設問×3 | ・ベクトルと図形(空間)(数学B) 設問×3 | ・ベクトルと方程式(平面)(数学B) 設問×3 |
| 3 | ・最大値・最小値、接線・法線(数学Ⅱ) 設問×3 | ・関数の増減と極値(数学Ⅲ) 設問×3 | ・領域と最大・最小(数学Ⅱ) 設問×3 |
| 4 | ・関数の増減と極値、微分法の方程式への応用(数学Ⅲ) 設問×2 | ・積分を含む等式、定積分(数学Ⅲ) 設問×4 | ・複素数の図形への応用(数学Ⅲ) 設問×3 |
| 5 | ・定積分と不等式、数列との融合、数列の極限(数学Ⅲ) 設問×4 | ・軌跡、体積(数学Ⅱ、Ⅲ) 設問×4 | ・面積、最大値・最小値(数学Ⅲ) 設問×3 |
確率の基本性質、ベクトルと図形、微積分法、領域が頻出分野です。
確率と図形問題という多くの受験生が苦手とする分野からの出題が多いので、重点的に対策していきましょう。
●対策
『青チャート』や『基礎問題精講』などの基本的な解法が載っている問題集を解いていきながら、これらの問題集にある解法を一瞬でアウトプットできるようになるまで反復していきましょう。
丸暗記するのではなく、一つ一つ「なぜこうなっているのか」ということを理解しながら頭に入れていってください。
ここで意味がわからないまま頭に入れても応用することができず、いくら勉強しても数学の成績が伸びないということになります。
上記の問題集が終わったら、『数学の良問問題集』や『数学重要問題集』で応用問題に取り組んでいきましょう。
ここでは、すぐに解答解説を見るのではなく、手を動かしながら問題をできるところまで解いていきます。
ここで一つも筋道がわからないということが連続する場合は、定石のインプットが甘い可能性がありますので、チャート式などに戻りましょう。
応用問題が終わったら過去問演習をしていきます。
解法が思い浮かぶ問題と浮かばない問題にわけ、前者の問題を確実に解けるようにします。
計算力に不安があれば、『合格る計算』シリーズで計算力をつけていきましょう。
GMARCH対策のまとめはこちら!↓