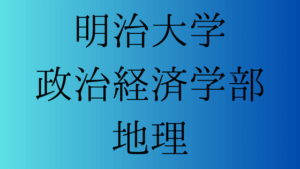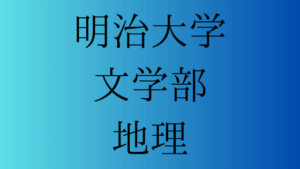明治大学 政治経済学部の政治経済対策
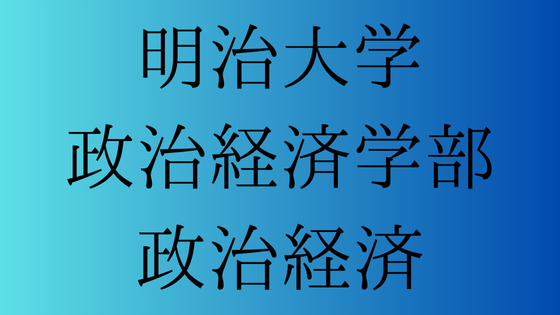
本記事では明治大学 政治経済学部の政治経済対策について記載しています。
政治経済の試験時間は60分で、配点は100点です。
目標得点率は70%以上に設定して勉強しましょう。
政治経済学部の情報(個別入試)
| 学科 | 年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
| 政治 | 2025 | 105 | 1,692 | 1,590 | 450 | 3.5 |
| 2024 | 105 | 1,132 | 1,057 | 453 | 2.3 | |
| 2023 | 105 | 1,642 | 1,540 | 450 | 3.4 | |
| 2022 | 105 | 1,377 | 1,284 | 508 | 2.5 | |
| 2021 | 105 | 1,611 | 1,519 | 460 | 3.3 | |
| 経済 | 2025 | 290 | 4,044 | 3,824 | 1,156 | 3.3 |
| 2024 | 290 | 3,779 | 3,564 | 1,137 | 3.1 | |
| 2023 | 290 | 4,418 | 4,204 | 1,204 | 3.5 | |
| 2022 | 290 | 3,685 | 3,490 | 1,329 | 2.6 | |
| 2021 | 290 | 3,484 | 3,293 | 1,057 | 3.1 | |
| 地域行政 | 2025 | 70 | 722 | 690 | 197 | 3.5 |
| 2024 | 70 | 769 | 730 | 223 | 3.3 | |
| 2023 | 70 | 534 | 511 | 160 | 3.2 | |
| 2022 | 70 | 632 | 598 | 189 | 3.2 | |
| 2021 | 70 | 486 | 464 | 145 | 3.2 |
*数値には追加合格・補欠合格・特別措置を含みます。
各項目の傾向と対策
大問は全部で4つです。
年度別の内容を確認しましょう。
・2025年度
| Ⅰ | 平和についての会話 | 10問(選択と記述) |
| Ⅱ | 中小企業の変遷 | 10問(選択と記述) |
| Ⅲ | 財貿易とサービス貿易 | 10問(選択と記述) |
| Ⅳ | 公害 | 10問(選択と記述) |
・2024年度
| Ⅰ | G7サミット | 10問(選択と記述) |
| Ⅱ | 環境問題に関するディベートの準備 | 10問(選択と記述) |
| Ⅲ | 物価 | 10問(選択と記述) |
| Ⅳ | 地球温暖化についての会話 | 10問(選択と記述) |
・2023年度
| Ⅰ | 司法権 | 10問(選択と記述) |
| Ⅱ | 「将来の働き方」についてのディスカッション、ベーシックインカムの実現可能性㈡関する議論 | 10問(選択と記述) |
| Ⅲ | 一物一価 | 10問(選択と記述) |
| Ⅳ | 日本国憲法を軸とした現代日本社会についての会話 | 10問(選択と記述) |
・2022年度
| Ⅰ | 選挙制度に関する会話 | 10問(選択と記述) |
| Ⅱ | 資本主義経済 | 10問(選択と記述) |
| Ⅲ | 国際貿易 | 10問(選択と記述) |
| Ⅳ | 人口の増加 | 10問(選択と記述) |
・2021年度
| Ⅰ | 主権国家体制 | 10問(選択と記述) |
| Ⅱ | GDP | 10問(選択と記述) |
| Ⅲ | 欧州の統合 | 10問(選択と記述) |
| Ⅳ | 高度経済成長~就職氷河期 | 10問(選択と記述) |
一問一答問題、選択問題、グラフ、表問題、計算問題など多様な形式で出題されます。
近年は特に資料を参照する問題や政治、経済の仕組みを整理して理解していないと解けない問題が多く出題されているので、参考書や問題集をただ解いていくだけの勉強で点を稼ぐのは難しいという状況です。
●問題別の分析
・記述問題
空所補充問題、一問一答問題で出題されます。
空所補充問題は文章中の空所に入る語句を記入する問題です。
空所の前後をみて当てはまる語句を記述していきましょう。
一問一答問題は実際に2023年度で出題された問題を見てみましょう。
下線部(7:所得税)に関連して、所得税にには農家・自営業・サラリーマン等の職種によって所得捕捉率が異なることで水平的公平性が損なわれるという課題がある。このような現象をカタカナ四文字で何と呼ぶか。もっとも適当と思われる語句を解答欄に記入せよ。
正解は「クロヨン」です。
サラリーマンの捕捉率を9、自営業者の捕捉率を6、農業所得者の捕捉率を4とみなす不公平感を指します。
以上のように参考書や一問一答などを使って正確に覚えておけば対応できます。
・選択問題
資料を読み取って解答する問題、一問一答問題、下線部に関する説明を選ぶ問題、計算問題などが出題されます。
一問一答問題は用語とその内容を正確に理解しておく必要があります。
資料問題は素早く正確に資料の内容を理解して、選択肢を吟味する必要があります。
その他、政治分野、経済分野両方で計算や仕組みをわかっていないと解けない問題などが出題されます。
実際に2023年度で出題された問題を見てみましょう。
下線部(1:裁定取引)に関して、スマートフォンが秋葉原で6万円、御茶ノ水で7万円で販売されている場合、その価格差が解消されていくのはなぜか。その理由としてもっとも適当と思われるものを次のなかから一つ選び、解答欄の記号(A~D)をマークせよ。
A. 秋葉原でスマートフォンの供給が増加し、御茶ノ水ではスマートフォンの需要が増加するため。
B. 秋葉原でスマートフォンの供給が減少し、御茶ノ水ではスマートフォンの需要が減少するため。
C. 秋葉原でスマートフォンの需要が減少し、御茶ノ水ではスマートフォンの供給が減少するため。
D. 秋葉原でスマートフォンの需要が増加し、御茶ノ水ではスマートフォンの供給が増加するため。
正解はDです。
秋葉原のスマートフォンを買って、御茶ノ水で売れば1台につき1万円の利益がつきます。
このような取引が増えれば秋葉原のスマートフォンの需要が増加し、スマートフォンの価格が上がります。
御茶ノ水では持ち込みが増加し、スマートフォンが売れ残るので(供給が増加する)、価格が下がります。
以上のようにして、価格差が解消されます。
以上のように裁定取引について正確に理解していないと、その理解を通じて問題を解くことができません。
過去問演習などを通じて応用問題にあたっていきましょう。
GMARCH対策のまとめはこちら!↓