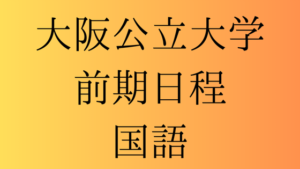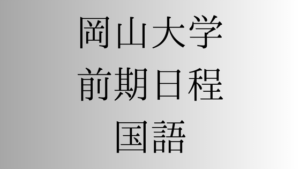大阪公立大学(前期日程)の小論文対策
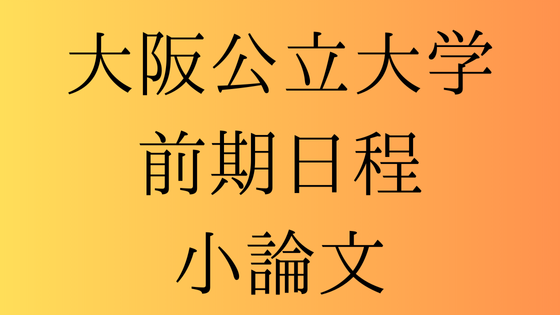
本記事では大阪公立大学(前期日程)の小論文対策について記載しています。
小論文は現代システム科学域の教育福祉学類・英・小論型で出題されます。
小論文の試験時間は120分で、配点は200点です。
大阪公立大学の入試情報
大阪公立大学の公式サイトをご参照ください。
各項目の傾向と対策
大問は全部で2つです。
問題と構成は下の表を参照してください。
| 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | |
| 第1問 | 出典A:厚生労働省「被保護者調査 月次調査」 出典B:「生活保護の行政記録と政府統計」藤原千沙・湯澤直美 1. Aの図から読み取れること(100字以内・20点) 2. 現行の世帯類型の定義および振り分けルールでは、具体的に見えにくい世帯の例を2つ挙げる(30点) 3. A、Bの資料をふまえて、生活保護受給世帯に対して求められる支援策について述べる(400字以内・50点) | 出典:『「みんな違ってみんないい」のか?ー相対主義と普遍主義の問題』山口裕之 1. 下線部について説明する(100字以内・20点) 2. 筆者が指摘する問題を説明する(200字以内・30点) 3. 相対主義の問題点を克服するためにはどうすれば良いかを述べる(500字以内・50点) | 出典:東京新聞TOKYO 森合正範、朝日新聞デジタル 忠鉢信一 1. 問題点の指摘(150字以内・30点) 2. 下線部の理由について説明する(120字以内・20点) 3. スポーツ指導や学校での部活動指導の具体的な改善方法について述べる(450字以内・50点) |
| 第2問 | 出典:『学校はなぜ退屈でなぜ大切なのか』広田照幸 1. 下線部と同じことを意味する部分を抜き出し、具体的な内容について経験をもとに記述(200字以内・25点) 2. 「個別最適化した学び」に対する「危惧」について要約(200字以内・25点) 3. 学校教育のなかに「個別最適化した学び」を取り入れることの是非と留意すべき点について記述(500字以内・50点) | 出典:「こども基本法」 1. 第三条の基本理念に関して、どのような問題が生じているか(100字以内・20点) 2. 問1の問題を解決する対応や方策(200字以内・30点) 3. なぜその提案が良いのかを論理展開(500字以内・50点) | 出典:「「認知症でもできること」から「認知症だからできること」へ. 『認知症とともにあたりまえに生きていく』丹野智文 1. 下線部について説明する(200字以内・30点) 2. 認知症の人に対して、家族や支援者が「管理や制限」をする理由を筆者はどう考えているか(100字以内・20点) 3. 自身の認知症の理解と問題文に書かれていることを比較し、違いや共通点を述べたうえで、今後の認知症の方への支援方法について述べる(400字以内・50点) |
総字数は2025年度は1400字、2024年度は1600字、2023年度は1420字でした。
現代文で出題されるような下線部について説明する問題や小論文特有の問題点の指摘、改善策の提案、提案の利点を述べるという構成です。
小論文は書いて練習することを嫌がり、後回しにしがちなので、はやめの対策をしていきましょう。
●小論文対策
各練習を始める前に文章の内容を理解する練習が必要です。
具体的な小論文対策に入る前に現代文の勉強をしていきましょう。
私立大学で出題されるようなマーク式の問題を解いて読解力を身につけて、国公立大学で出題されるような記述タイプの問題に移っていきましょう。
記述タイプの問題では傍線部のことについて説明する問題がよく出題されるので、本学部の小論文対策になります。
記述力をつけた後は、具体的に自分の意見を理由付きかつ指定語数内で答えられるように練習していきます。
過去問の数が少ないため、普段から様々な社会問題について自分の主張と改善策を考える習慣をつけておいてください。
実際に書くときは作文にならないように注意してください。
自分の意見を例の提示や実際のデータ、事実なしで勝手に思ったことを書くことが作文です。
自分の中にある感情や思ったことを中心に書くのではなく、本問で提示された社会的事象を中心に書いていきましょう。
幸い、本学部の小論文は問題点の指摘から設問が始まっていることが多く順を追って確認していけば文章を書くことができるような構成になっています。